「これってハラスメント…?」
職場での嫌がらせや不快な言動に悩んでいても、「どこからがハラスメントなのか分からない」「誰に相談すればいいのか迷っている」という方は多いのではないでしょうか。対応を間違えると、自分の立場が不利になったり、問題がこじれる可能性もあるため、慎重な判断が求められます。
本記事では、職場のハラスメントに正しく対応するための5つのステップを具体的に解説します。あわせて、よくあるハラスメントの種類や実際の事例、相談窓口の活用方法についても紹介します。
いつまでも我慢する状態は良くありません。自分が嫌だと感じた時からもう、ハラスメントは始まっています。
自分や周囲の人を守るためにも、正しい知識と行動を身につけましょう。
職場のハラスメントとは?その定義と種類

ハラスメントの基本的な定義
厚生労働省の資料によると、職場におけるハラスメンとの定義は
- 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
- 業務の適正な範囲を超えて行われること
- 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
上記①~③すべての要素を含む行為です。
3つの要素のいずれかを欠く場合であれ ば、職場のパワーハラスメントには当たらない場合があるので注意すること。
ハラスメントは明確な線引きが難しく、見逃されやすいため、定義を正しく理解することが重要です。
職場で起こりやすいハラスメントの種類
職場で頻繁に見られるハラスメントにはいくつかの種類があります。
それぞれの特徴を知っておくことで、早期発見と適切な対応がしやすくなります。
パワーハラスメント(パワハラ)
職務上の優位な立場を利用し、部下や同僚に対して行われる嫌がらせです。暴言や過度な叱責、業務の過剰・過少な割り当てなどが含まれます。
要領や覚えが悪い社員にイライラした上司が「ばか、そんなこともできないのか!」とひどい罵倒を毎日のように繰り返す。酷い時には蹴り付ける、書類で頭を叩く、などという言葉だけでない暴力行為を受けたケースも。
②業務の適正な範囲を越えて行われること、が適用されるかどうかが争点になるでしょう。
指導と称して行われることもあり、判断が難しいケースもあります。
セクシャルハラスメント(セクハラ)
性的な言動により、不快な思いや職場での居心地の悪さを与える行為です。冗談のつもりでも、相手が不快に感じた時点でセクハラになる可能性があります。
女性の被害が良く取り上げられますが、男性が被害を受ける場合も多くあります。
彼女の有無を聞かれる、容姿について揶揄われる、男らしさを過度に要求される、女性の上司が執拗に食事や飲みに誘ってくる。
露出度の高い洋服をきて職場にくるのも、男性へのセクハラになる場合があります。
マタニティハラスメント(マタハラ)
妊娠・出産・育児に関することで、不利益な扱いや嫌がらせを受けることを指します。産休や育休を理由に職務内容を変えられる、昇進に影響するなどが該当します。
嫌味を言われたり、辞めた方がいいんじゃないか、と案に退職を迫るような物言いをされたり、といったケースが良くあるようです。
モラルハラスメント(モラハラ)
言葉や態度によって精神的に追い詰める行為です。
無視や陰口、仲間外れにするなど、表面的には分かりにくいものが多いのが特徴です。
ハラスメントの見分け方と事例

ハラスメントに該当するかどうかの判断基準
ハラスメントかどうかを判断する際には、加害者側の意図よりも被害者側の感じ方が重視されます。
また、その行為が継続的に行われているか、職場の環境に悪影響を与えているかという観点も重要です。
個々のケースによって異なるため、複数の視点から冷静に判断することが求められます。
実際にあった職場のハラスメント事例
現実の職場では、さまざまなハラスメントが発生しています。その一部を紹介します。
上司からの叱責がパワハラとされた事例
ある企業では、上司が部下に対して業務中に繰り返し強い口調で叱責を行い、部下が精神的に不調を訴える事態になりました。
社内調査の結果、パワハラと認定され、上司には懲戒処分が下されました。
セクハラ発言による人間関係の悪化事例
男性社員が女性社員に対して日常的に容姿についてのコメントを繰り返し、周囲が注意を促してもやめなかったケースです。
最終的に女性社員は部署異動を希望し、職場の雰囲気も悪化しました。
同僚間の無視・孤立が問題になったケース
特定の社員に対して、複数の同僚が意図的に業務連絡を回さない、雑談に加えないなどの行動をとり、結果としてその社員が職場で孤立した事例もあります。
これもモラハラと認定され、部署内の再教育が行われました。
職場でハラスメントを受けたときの5つの対応ステップ

ステップ1:証拠を残す(記録・録音・メール保存など)
最初に行うべきは、ハラスメントの証拠を残すことです。
具体的な日時や内容、相手の発言や態度、自分の気持ちなどを記録しておくと、後の相談や調査で大きな助けになります。
可能であれば録音やメールの保存も有効です。
ステップ2:信頼できる人に相談する
一人で抱え込まず、信頼できる上司や同僚、家族などに相談しましょう。
第三者の意見を聞くことで、客観的に状況を判断できるようになります。
また、相談記録があることで、自身の行動にも正当性を持たせることができます。
ステップ3:社内の相談窓口を利用する
多くの企業にはハラスメントに対応する相談窓口が設けられています。
人事部やコンプライアンス担当など、しかるべき部署に状況を説明し、正式な対応を依頼することができます。社内での解決を図る第一歩となります。
ただし、これは社内の相談窓口がしっかりと機能していれば、というのが前提です。
というのも、実際は社内の相談窓口に不満を感じている人も多くいるからです。
「もう少し我慢できない?」と聞かれた。「勘違いってことはないですか?」と言われた、すぐに上司に報告されて隠蔽されたと、いう酷い例もあります。
まずは相談窓口に行って話をしてみて、隠蔽体質などがほの見えたら、外部の相談窓口を頼るようにしましょう。
ステップ4:外部の相談窓口に連絡する
社内での解決が難しい、もしくは会社が適切に対応してくれない場合は、外部機関を活用しましょう。
厚生労働省や労働局には無料で相談できる窓口があります。中立的な立場でアドバイスを受けられるのが利点です。
ステップ5:法的手段を検討する場合のポイント
状況が深刻な場合や、会社側が明らかに不当な対応をしている場合には、弁護士など専門家の助けを得て法的措置を検討することも選択肢です。
その際には、これまでの対応履歴や証拠の整理が重要になります。
以下を参考に証拠を集めておきましょう。
- 小型の録音機やカメラで音声や映像を残しておく
- 日々受けた被害、その時の状況や感じたことを日記に記録しておく
- 受信したメールやLINEのバックアップを取る
- 電話の場合は録音しておく
ハラスメントへの対応でやってはいけないNG行動

感情的に反応する
怒りや悲しみがあっても、感情的に相手にぶつけてしまうと、逆に自分が不利な立場に立たされることがあります。
感情的になるとどうしても思考回路が一方向になりがちで、冷静な判断ができなくなります。言わなくても良いことまで口走ってしまったり、職場で喚き散らす迷惑な人、というレッテルをはられてしまったという人もいます。
冷静な対応を心がけ、証拠を積み上げることが最優先です。
証拠がないまま訴える
状況を変えたい一心で証拠がないまま訴え出ると、言い分が通らないこともあります。
裏付けのない主張は信用を失いやすく、逆効果になるリスクもあるため、記録の重要性は非常に高いといえます。
最近は通販でボールペン式の録音機や小型のカメラなどが簡単に入手できる時代です。
これらのアイテムを手に入れてしっかり証拠を固めておきましょう。
毎日起こったこと、感じたことを詳細に日記に記録しておくこともおすすめです。
放置し続けてしまうことのリスク
「自分さえ我慢すれば」と思って放置していると、ハラスメントが常態化し、自分の心身の健康に大きな影響を与える恐れがあります。早めの対応が自分を守る最良の方法です。
また放置してしまうことで、社内自体がその状況をいつの間にか受け入れ、味方だと思っていた同僚がいつの間にか場の空気に流されて加害者化せざる得ない状態になってしまったり、と、被害が拡大していってしまう恐れもあります。
自分だけのことではない、という気持ちになれば動けるということもあるので、同僚や後輩たちのために、という気持ちになることも、ハラスメントに対抗するための原動力には有効かもしれません。
ハラスメントに悩んだら相談すべき窓口一覧
企業内の相談窓口(人事部・相談室など)
勤務先に設けられている内部の相談窓口は、まず最初に頼るべき場所です。匿名相談を受け付けている企業も多く、相談の記録が今後の対応に活かされます。
社内に相談窓口がない場合や信用ができないという場合は厚生労働省や労働局の相談窓口を利用しましょう。
厚生労働省の相談窓口
厚生労働省では、「総合労働相談コーナー」などでハラスメントの相談を受け付けています。
無料かつ中立な立場で対応してくれるため、社内に相談しづらい方にも適しています。
労働局や労働基準監督署の活用方法
労働局や労働基準監督署も、労働環境に関するトラブルの相談窓口を持っています。
状況に応じて企業への指導や立ち入り調査が行われることもあります。
相談場所は会社がある地域の労働局または労働基準監督署の総合労働相談コーナーです。
弁護士や労働問題に強い専門家への相談
法的な対応を視野に入れる場合は、労働問題を専門とする弁護士に相談するのが有効です。
無料相談を実施している自治体や弁護士会もあるため、まずは問い合わせてみるとよいでしょう。
まとめ|職場のハラスメントは早めの対応がカギ

普段からの関係性の構築も大事
ハラスメントは一方的な被害を受ける場合もありますが、普段から良好な関係性を保っていれば避けられていた可能性がある、というケースもあります。
例えば、マタハラ。
妊娠、出産、育児で休暇を取る場合はどうしても長期になってしまいます。
頼りになる存在であればあるほど、その空いた穴は大きく、残された側は不安になり、気持ちが乱れてしまうこともあるでしょう。
不安から嫌味を言ってしまったり、無視してしまったり、ということもあります。
普段から産休や育休について話をしたり、いざとい時のために誰もがわかりやすいマニュアルを用意しておくなどして、相手の不安感を和らげる行動を示すことで不快な思いをせずにすむ可能性があるかもしれません。
早期対応が被害の拡大を防ぐ
ハラスメントは、放置すればするほど深刻な状況になりかねません。
早期に正しい対応をとることで、被害を最小限に抑え、精神的な負担も軽減できます。
今回ご紹介したステップを参考にして冷静に、速やかに対応してください。
正しい知識と準備で自分を守ろう
ハラスメントは誰にでも起こり得る問題です。
正しい知識を持ち、適切なステップを踏むことで、自分の身を守るだけでなく、職場全体の環境改善にもつながります。
少しの行動が、未来を大きく変える一歩になるかもしれません。



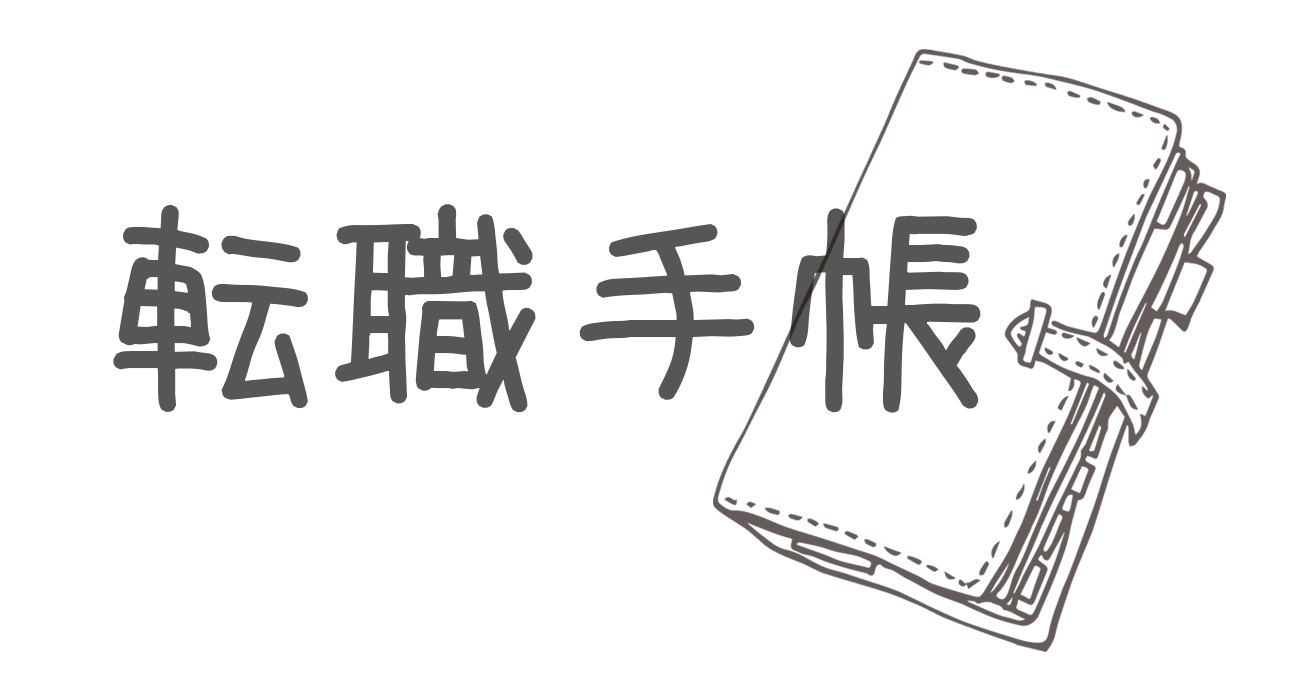

コメント