会社を辞める!悩んで悩んでようやく決心がついたけれど、次に悩むのは「どうやって伝えよう…」ですよね。
「どのタイミングで伝えればいい?」「どう言えばスムーズに辞められる?」「引き止められたらどうしよう」そんなことばかり考えて、不安でモヤモヤしていませんか?
退職は人生の大きな決断。だからこそ、上司への切り出し方や伝え方には慎重になって当然です。
結論から言うと、退職の意思をスムーズに伝えるには、いくつかの“コツ”を押さえるだけで大丈夫!
この記事では、退職を伝えるベストなタイミングや言い方、上司への伝え方の例文、メールでのマナーまで、具体的な方法を5つのポイントにまとめて解説します。
「会社を辞めるときに困らない、気まずくならない伝え方」を知りたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
退職を切り出す前に考えておくべきこと|ポイント1

なぜ会社を辞めたいのか理由を整理する
退職を伝える前に、まず「なぜ辞めたいのか」を明確にすることが大切です。
転職や独立、家庭の事情など理由はさまざまですが、自分の気持ちを整理しておくことで、上司に対してブレのない伝え方ができます。
よくあるのが「なんとなく辞めたい」という感覚だけで行動して、結局引き止められて曖昧になり、辞められないままになる、というケースです。
「どうして辞めたいの?」「なぜ?」と上司から聞かれるのは当たり前。
人材の入れ替えに消極的な会社なら、強く引き止められる、という場合もあります。
特に環境面や待遇面で辞めるという話を切り出したときには、環境や待遇の改善や異動などを提案されてしまうことも。
上司の質問や提案に対してはっきりと自分の意思を最後まで伝え切れるかがカギになります。
そのためにはまずは自分の意思を何度も確認しておくことです。紙に書き出すのも効果的なので、ぜひ実践してみてください。
上司に辞める理由を詳細に告げる必要はありませんが、一身上の都合であったとしても「詳細は控えさせていただきますが、一身上の都合で辞めさせていただきたいです!」としっかり意思表示できるようにしておきましょう!
退職の希望時期を明確にしておく
いつ辞めたいのかを事前に決めておくことで、スムーズな伝達が可能になります。
「来月中に退職したい」「〇月末までは勤務可能」といった希望を持っておけば、上司との相談も具体的になります。
企業によっては就業規則で「1ヶ月前に申告すること」と定められている場合もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
引き継ぎや業務整理の準備も大切
退職を伝える段階で、引き継ぎの準備をある程度考えておくことも重要です。
後任が見つかるまでに必要な資料や業務の棚卸しを把握しておけば、上司からの印象も良くなり、円満な退職につながります。
辞める側の誠意が伝わるかどうかは、こうした細かい準備にかかっています。
上司への退職の伝え方とタイミングのコツ|ポイント2

最初に伝えるのは誰?上司への順序に注意
退職の意志は、まず直属の上司に伝えるのが基本です。
同僚や他部署の人に先に話すと、噂が広まり、上司の耳に間接的に入ってしまう可能性があります。これは信頼関係を損なう原因となるため、最初の伝え方の順序には十分注意しましょう。
ベストなタイミングとは?退職を伝える時期の目安
退職を伝えるベストな時期は、繁忙期を避けたタイミングです。
余裕を持って1〜2ヶ月前に相談できると、引き継ぎもしやすくなり、職場の負担も軽減されておすすめです。
事業主である私のリアルな意見を言わせてもらうと、新たな人員補充の準備や仕事の引き継ぎ、退職時の手続きのことなどを考えると、やはり辞める意志が固まったら早めに伝えてもらえるほうが助かりますし、誠意や配慮を感じて好印象を持ちます。
また、上司との面談は終業前や週末前を選ぶことで、落ち着いて話しやすく気持ちを伝えるには最適です。
NGなタイミングや伝え方とは
繁忙期はもってのほか!
繁忙期以外の通常業務時でも忙しいときや、会議前、トラブルの対処中などの緊迫したタイミングでの報告は避けましょう。
また、LINEや社内チャットでいきなり「辞めます」と伝えるのはマナー違反。
退職は重要な報告なので、直接会って伝えるか、最初の一歩として丁寧なメールで面談のお願いをするのが理想的です。
面談の依頼をするメールには、上司の都合の良い日時を指定して欲しい旨を伝えることも忘れずに。
スムーズに退職を切り出す言い方・例文|ポイント3

対面で伝える場合の切り出し方と例文
面談の場では、まず感謝の言葉から入ることで相手への配慮が伝わります。
「お忙しいところお時間をいただきありがとうございます。今日は大切なお話がありまして、時間をいただきました」と前置きした上で、
「このたび、〇月末を目処に退職させていただきたいと考えております」と率直に伝えると、誠実な印象になります。
前置きがあることで自分自身も落ち着くことができますし、緊張と不安からまず何から話せば良いのかわからない、という状況を回避できますよね。
メールで伝えるときの注意点と文例
どうしても対面で話す機会が取れない場合は、退職の相談を持ちかけるメールを送るのも一つの方法です。
ただし、メールの内容はできるだけ丁寧に、かつ端的にまとめることが大切です。
件名の付け方のポイント
件名には「ご相談のお願い(〇〇より)」や「退職についてのご相談」など、内容がすぐに伝わる表現を用いましょう。
「至急」や「重要」といった強い言葉は避け、冷静なトーンで書くことが望ましいです。
本文の構成と丁寧な言い回し
本文では、最初に感謝の意を伝え、次に退職の意思を簡潔に述べます。
「突然のご連絡失礼いたします。日頃よりご指導を賜り誠にありがとうございます。実は、一身上の都合により退職を検討しており、一度ご相談のお時間をいただけますと幸いです」
というように、丁寧な言い回しを心がけましょう。
いくら上司が多忙であったとしても、最初のメールから「⚪︎日付けて退職させていただきますので、よろしくお願いします」といった一方的な内容にならないように気をつけてくださいね。
トラブルを避ける退職の伝え方のマナー|ポイント4

感謝の気持ちを忘れずに伝える
どのような事情であれ、これまでの経験に対する感謝の言葉は忘れないようにしましょう。
「お世話になりました」「貴重な経験をさせていただき感謝しています」といった一言が、退職後の人間関係にも良い影響を与えます。
引き止められたときの対処法
退職を申し出ると、上司から引き止められるケースもあります。
その際は、動揺せずに「すでに意思は固まっております」と伝えることが大切です。
ただし、相手の話を一度受け止めた上で、自分の考えを丁寧に説明することで、感情的な対立を避けることができます。
例えば業務に対しての不満や、人間関係の拗れが原因で退職を希望している場合はつい感情的になりがちですが、落ち着いた調子で話をするほうが気持ちも伝わりやすく、相手も深刻に受け止めて、執拗な引き止めに合わない可能性が高いです。
円満退社のために意識したいポイント
円満に退職するには、常に冷静で礼儀正しい姿勢を心がけることが重要です。
引き継ぎを丁寧に行い、最後まで誠実に仕事に取り組むことで、職場に良い印象を残すことができます。
退職の伝え方だけでなく、その後の行動にも配慮が求められます。
退職後にトラブルを防ぐためのフォローアップ|ポイント5

引き継ぎの資料・連絡先の共有
業務の引き継ぎはできる限り文書化し、誰が見ても分かる形にまとめておくと安心です。
また、取引先や関係部署への連絡先も整理し、後任者への橋渡しを丁寧に行うことで、退職後のトラブルを防ぐことができます。
社内・関係者への挨拶の仕方
退職日が近づいたら、社内外の関係者に対して感謝と今後の連絡先を伝える挨拶を行いましょう。
対面や電話、またはメールでの丁寧な挨拶は、信頼関係を継続するうえで非常に大切です。
やめたら関係なし、ではなく、自分が辞めた後も同僚や先輩後輩が働きやすい環境を続けてもらえるように、という思いで行動しましょう。
立つ鳥跡をにごさず、です!
社会保険や年金などの手続きの確認
退職に伴い、健康保険や厚生年金、雇用保険などの公的手続きも必要になります。
会社からの説明を受けた上で、自分でも各種書類の提出時期や方法を確認し、漏れのないようにしましょう。
退職後の生活をスムーズにスタートさせるためにも、ここはしっかり押さえておきたいポイントです。
まとめ

退職は決して後ろ向きな行動ではなく、新たなスタートの一歩です。
退職の意向を上司に伝えるときには恐怖感、罪悪感、不安感、色々な負の感情が渦巻いていることも多いでしょう。
ですが、正しい「伝え方」と誠意ある対応を意識することで、円満に会社を辞めることができます。
この記事を読んで、気持ちの良いスタートを切りましょう。
最後に、退職の意向を伝える時に一番大切なこと
- 感謝
- 誠意
- 配慮
この3つを忘れずに行動すれば円満退職はまず間違いなしです!



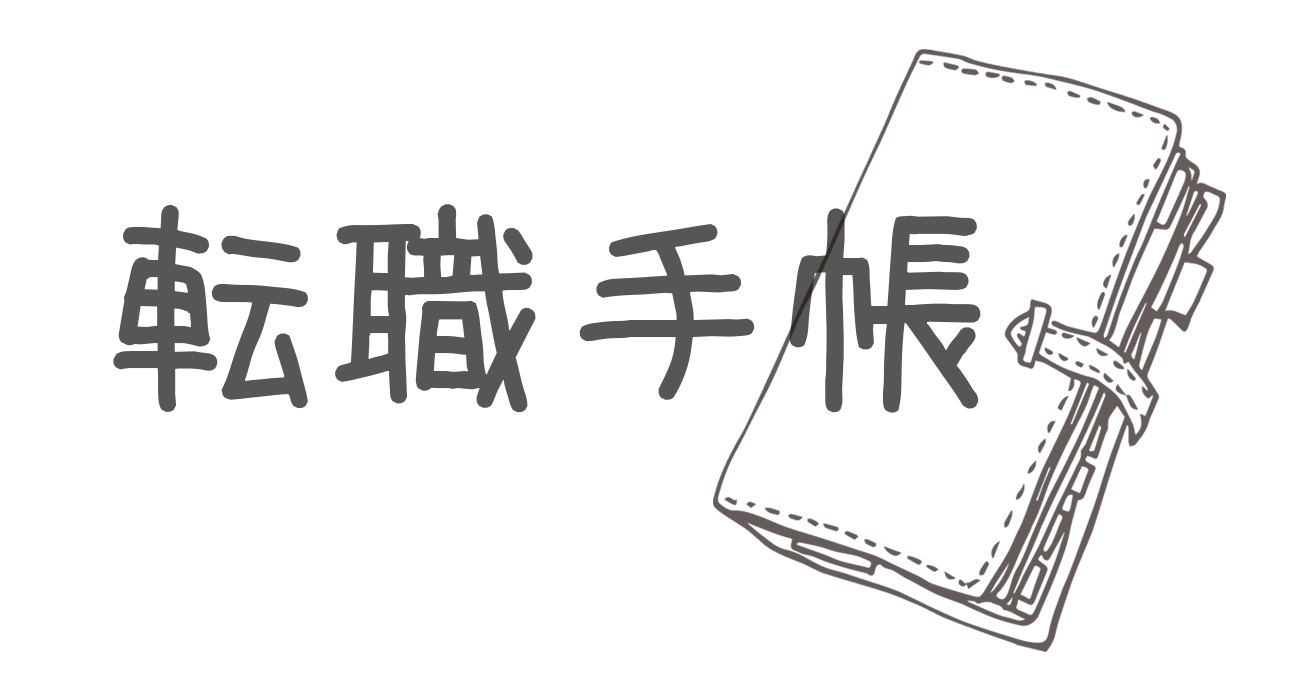

コメント